こんにちは、ヒロタカです。
薬局や病院で臨床経験を積み、今は研究や経営の勉強を続けています!FP3級の資格も持っています。
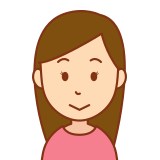
病院だと夜勤があるし、薬局だとシフトがあるじゃない?
毎日、9時17時で働く人に比べると、大変な気がするわ!
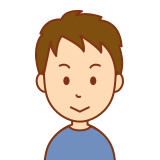
確かに、薬剤師は夜勤やシフトのある職場で働くことも多いよね。
この記事では、夜勤やシフト勤務が生活に及ぼす影響について、紹介するよ!
・夜勤やシフト勤務は不健康?
・夜勤やシフト勤務を選択するのはどんな人?
・柔軟性のある働き方とは
この記事を読めば、柔軟性を持った働き方を選べるようになります。
(※本記事は、イチロー・カワチら著、「社会疫学<上> 第5章「労働環境と健康」を参考にしています。)
夜勤やシフト勤務は不健康?
睡眠不足
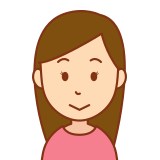
夜勤が入ると、生活リズムが崩れちゃうのよね…。
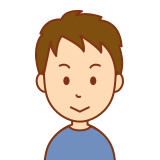
そうだね。
夜勤やシフト勤務があると、睡眠不足になりやすいよね。
不規則な勤務スケジュールは、睡眠不足を引き起こします。
睡眠不足は、代謝異常、循環器疾患、事故などの不健康な結果につながることが分かっています。
例えば、シフト勤務は、心筋梗塞や虚血性発作のリスク上昇と関連が認められたそうです。(Vyasら、2012)
習慣を作ることが難しい
不規則な勤務スケジュールは、日々の習慣を妨げます。
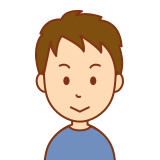
例えば、遅番(12時から21時など)の翌日、早番(8時から17時など)がある場合を考えてみよう!
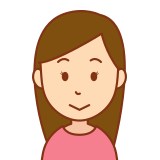
帰って夕食を食べてお風呂に入ると、もう23時。
夕食を遅く食べると、翌朝あまりお腹も空かないのよね。朝食を食べないことも多いわ…。
このように、シフト勤務は食事や睡眠、入浴など、日々の習慣形成に大きな影響を与えます。
同僚とのコミュニケーションが減る
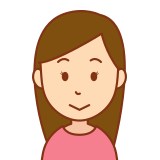
シフトだと、昼休みが被らないじゃない?
薬局の休憩室で、一人でご飯を食べるのが、悲しくなるときもあるわ。
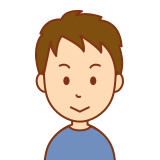
たしかに!
大きい薬局でも、意外と休憩中の会話は少なかったりするよね。
シフト勤務は、薬剤師が働くにあたって、同僚から孤立する要因の一つです。
勤務中、かかりつけ患者さんへの応対は行っている一方で、
日々一緒に働いているはずの同僚のことをあまり知らない…なんてこともあるのではないでしょうか。
夜勤やシフト勤務を選択するのはどんな人?
体は不健康になりやすい一方で、社会的に良い側面もあります。
家族の時間を確保しやすい
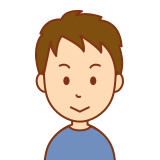
シフト勤務には、働く時間を選べるというメリットがあるよね。
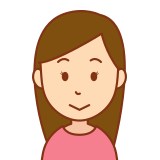
たしかに!
夫と働く時間をずらして、子どもを一人にしないようにしているわ。
シフトを選択することができる場合、自分や家族に必要な時間を確保することができます。
介護や子育てをしているときには、シフト勤務のありがたさを感じる人も多いのではないでしょうか。
賃金が高い
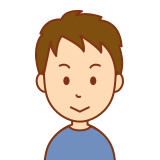
若いうちは、より多く稼ぐために、夜勤に多く入っていたよ。
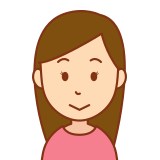
夜勤手当や時間外手当って、結構大きい額になるわよね。
病院や都市部の薬局では、24時間の医療サービスが求められています。
夜勤やシフト勤務は健康に負担がありますが、需要に対応するために賃金が高く設定されています。
柔軟性のある働き方とは
このように、夜勤やシフト勤務には不健康な側面がありますが、働き方の選択肢としてはメリットがあります。
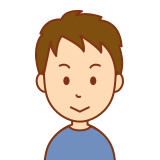
自分でシフトを選べたり、夜勤の頻度を決められると良いのかも?
ここで、仕事における「柔軟性」とは以下のように定義されます。
仕事を行うタイミング、ペース、場所を、自らの裁量で決定できること。(Greenhaus & Powell, 2006)
例えば、シフト勤務の場合、始業・就業時間を自分で決められるという柔軟性がある、ということができます。
もちろん、病院や薬局側の都合で勤務スケジュールが決まることはあります。
しかし、自分が選んで入職した病院や薬局が決めたシフトであることを思い出しましょう。
そうすると、柔軟性を持った働き方ができていると感じられるかもしれませんね。
(一方で、雇用者側は、労働者にとって柔軟な働き方を提示する努力が必要です。)
まとめ
今回は、夜勤やシフト勤務が生活に及ぼす影響について紹介しました。
皆さんも、社会疫学に関する知識を学んで、より良い人生を歩んでいきましょう!
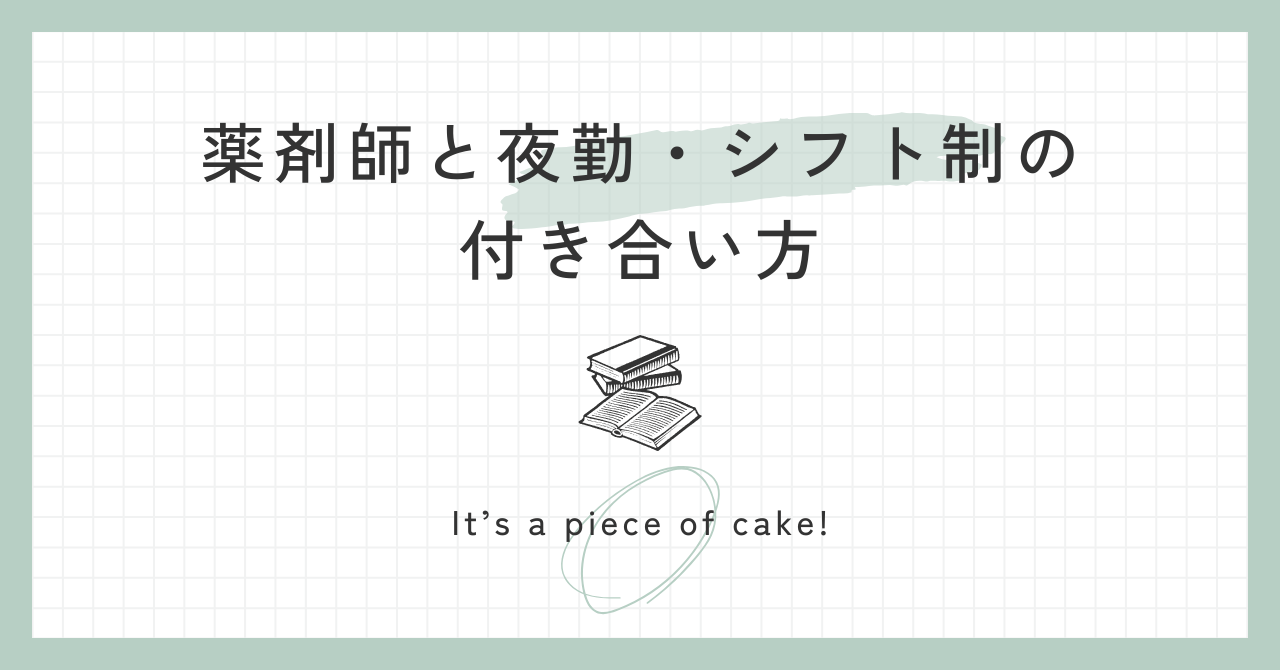

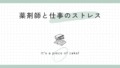
コメント